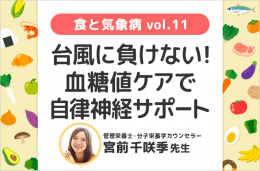抜け毛・だるさ・気分の落ち込み…秋バテケアにおすすめの食事法3選
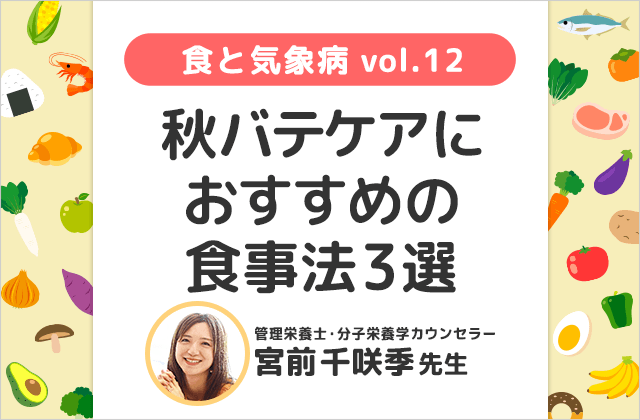
秋バテの原因とは?
夏の疲れが残っている
真夏の猛暑は、体温を下げようと自律神経をフル稼働させます。交感神経が優位になると、副腎から「コルチゾール」というホルモンが分泌され、体をストレスと戦うモードに切り替えます。この仕組み自体は自然なものですが、連日の暑さ・紫外線・冷房などが重なると、交感神経と副腎が休む暇なく働き続けてしまいます。その結果、秋になってもだるさや疲労感が残りやすくなるのです。
ミネラル不足
もうひとつ見逃せないのが、汗と一緒に流れ出てしまうミネラル不足です。特に 鉄とマグネシウム が不足すると、心身の不調につながりやすくなります。
鉄はエネルギーを生み出すために欠かせない栄養素であり、血液をつくる材料でもあります。さらに「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの合成や、肌や髪の健やかな成長にも関与しています。そのため不足すると、疲れやすさや気分の落ち込み、イライラ、抜け毛や肌荒れといった不調の一因になることがあります。特に女性は月経によって鉄を失いやすいため、普段から意識的に補うことが大切です。
一方、マグネシウムはエネルギー代謝やセロトニン合成を助けるほか、筋肉や神経の働きを調整する役割があります。不足するとだるさや気分の不安定さに加えて、筋肉のこわばりや疲労にもつながりやすくなります。鉄と同じく、マグネシウムも毎日の食事で意識して摂りたい栄養素です。
激しい寒暖差
秋は一日の気温差が大きく、朝晩は冷え込むのに昼は汗ばむほど暑い日もあります。
このような急激な寒暖差は、自律神経にとって大きなストレス。体温を一定に保とうと何度もスイッチを切り替えるため、結果的に疲労が蓄積しやすくなります。
「なんとなくだるい」「気分が落ち込みやすい」といった秋特有の不調の背景には、こうした自律神経の疲れが隠れていることもあります
秋バテを乗り切る食事の工夫
ビタミンCで副腎をサポート
ビタミンCはストレス対応で働く副腎に多く含まれ、消耗しやすい栄養素です。
ブロッコリーやパプリカ、キウイ、柿などは手軽に食卓に取り入れられるため、積極的に摂りましょう。ビタミンCは熱で壊れやすいなど量を確保しにくい栄養素でもあるため、サプリメントを取り入れるのも一つの方法です。
マグネシウムで疲労をサポート
海藻、豆類、種実類に豊富なマグネシウムは、エネルギー産生やメンタルの安定に欠かせません
わかめや大豆、アーモンドなどを日常の中で「ちょい足し」する工夫が、疲労感の軽減につながります。忙しいときは、コンビニで買えるアーモンド小袋や豆乳飲料も便利です。
私自身は液体のにがりを汁物に数滴入れて飲んだり、硫酸マグネシウム(エプソムソルト)をお風呂に入れて皮膚からも吸収できるよう心がけています。ストレスや汗によって簡単に失われやすい栄養素だからこそ、日常的に意識して補うことが大切です。
鉄でエネルギーの土台づくり
鉄もエネルギー産生とメンタル安定の要です。レバーや赤身肉、赤身魚、あさり缶などを献立に取り入れると、不足を補いやすくなります。
例えば「牛肉とピーマンの炒め物」や「あさりの味噌汁」は、普段の食卓に無理なくプラスできるメニューです。
レバーが食べられる方は、特におすすめの食材です。私は週1回、必ずレバーを食べる習慣をつけています。意外と値段もお手頃で調理法もシンプルなので、ぜひ挑戦してみてください。苦手な方は、ハンバーグに細かくしたレバーを混ぜるなど料理に混ぜ込む形から始めると食べやすいですよ。
まとめ
秋バテは「夏の疲れ」「ミネラル不足」「寒暖差ストレス」が重なって起こりやすくなります。「秋だからしょうがない」と諦める方もいますが、栄養を意識した食事を取り入れることで、コンディションアップを狙うことができます。
大切なのは「完璧にやること」ではなく「できることから少しずつ始めること」です。朝食にフルーツをプラスする、味噌汁に海藻を加える、週に一度は鉄を含む食材を食べる…そんな小さな工夫でも、体はきちんと応えてくれます。
季節の変わり目は、どうしても心身のバランスを崩しやすい時期です。だからこそ、日々の食事で自分を労わる習慣を持つことが大切です。栄養を意識しながら、自律神経に優しい生活を送ることで、きっと体も心も軽やかに、秋を快適に過ごせるはずです。