それ、「季節性うつ」かも?食事でできる心のケア3選
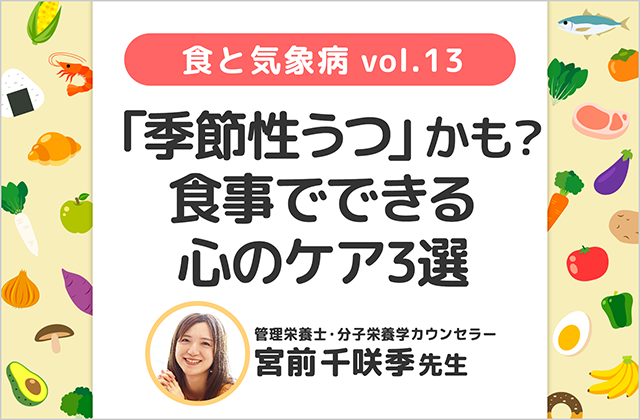
冬に増える「季節性うつ」とは?
日照時間が減ると、脳内のセロトニンが減少
「なんだかやる気が出ない」「朝起きるのがつらい」「甘いものが無性に食べたくなる」こんなお悩みはありませんか。症状が冬になると強まる人は、季節性うつと関連があるかもしれません。
原因のひとつは、日照時間の減少。太陽の光を浴びることで脳内で作られるセロトニンという神経伝達物質は、気分を安定させる「幸せホルモン」。
日照が減る冬は、このセロトニンの分泌が少なくなり、気分が沈みやすくなると考えられています。
また、セロトニン不足は睡眠ホルモン「メラトニン」の不足にもつながります。睡眠の質が下がることで朝がしんどくなったり、日中のだるさや集中力の低下を感じる人もいます。
寒暖差や気圧の変化も、心と体にストレスを与える
冬は寒暖差が大きく、気圧も下がりやすい季節。こうした変化は自律神経に負担をかけ、血流や体温の調整がうまくいかなくなることがあります。
それによって起きる体の冷えや肩のこり、頭の重さといったプチ不調から、気分にも影響することも。
つまり、冬の「なんとなくしんどい」には、日光・気温・気圧と色々な要因が関わっているのです。
食事でできる心のセルフケア
セロトニンを支える「たんぱく質」

まずはセロトニンの材料を摂ることが大切です。セロトニンは、食事からとるトリプトファン(アミノ酸)を材料に作られます。
卵、納豆、豆腐、魚、肉など、たんぱく質を多く含む食材を食事に取り入れることが大切です。手のひら1枚にたっぷり乗る量を、毎食摂りましょう。
さらに、トリプトファンからセロトニンを合成するには鉄やビタミンB群などの栄養素も必要です。赤身の魚(まぐろなど)やレバーは、たんぱく質、鉄、ビタミンB群が一度に摂れる優秀な食材。積極的に取り入れましょう。
ビタミンD不足に注意
冬のメンタル低下に深く関わる栄養素のひとつがビタミンDです。
ビタミンDは、日光を浴びることで体内で作られますが、日照時間が短くなる冬は不足しがち。
ビタミンDが少なくなると、セロトニンの働きが低下し、気分の落ち込みを感じやすくなることが知られています。
食事からとるなら、鮭、いわし、卵黄、干ししいたけなどがおすすめです。しかし実際は、1日に必要な量を食事だけでとるのは難しい栄養素。サプリメントも上手く組み合わせ、必要量を満たせるよう意識しましょう。
腸から整える「発酵食品」
最近の研究では、腸内環境とメンタルの関係も注目されています。
腸には「腸内セロトニン」と呼ばれる神経伝達物質が多く存在し、腸内環境が乱れると気分の安定にも影響することがわかってきました。
味噌、納豆、キムチなどの発酵食品を日々の食事に加え、腸内環境を整えることで心も穏やかに保ちましょう。
まとめ
冬は、日照の少なさや気温の変化などで、心も体もゆらぎやすい季節。
セロトニンを支えるたんぱく質とビタミンB群、そしてビタミンDや発酵食品を意識してとることで、内側から心の安定をサポートできます。
気分が落ち込みがちな時期こそ、あたたかい食事で体をいたわり、心にも栄養を届けてあげましょう。






